シン・ロジカルシンキング
今回はシン・ロジカルシンキングという本を読みました。この本を読もうと思った動機としては、自分にロジカルシンキングが足りていないのではないかと思ったからです。
整理していくと、まず私が行っているDSという職業はデータを分析して、それをもとに仮説検証を行って事業を回すというところです。事業の内容についてはあまり細かくは言いませんが、なぜこの仮説を立てたのか、そのために何のデータが必要で、どんな検証方法が必要で、どういう検証方法や分析ツールを使ったのか、そういうところを明確に話す必要があります。
また、私は新人なので、その仮説検証や仮説の立て方、検証方法、検証ツールが正しいかどうかは、上長に確認したり、同期間できちんと揉む必要があります。その際に、自分がなぜそう考えたのか、なぜそのツールを使おうと思ったのかというのが曖昧では、相談された方も良い時間の使い方ができないと考えています。そのため、自分の考えをきちんと論理的に整理する必要があります。
論的に確かにそうだねと思ってもらえるように考える必要があります。その一方で、それだけだと私がやる理由ってどこにあるのかなというふうにも思います。つまり、今のAIであればある程度の分析は、正しいか正しくないかを置いておいて、それっぽいものは作れる状況です。ロジカルシンキングについても、場合によってはAIの方がうまくいくかもしれません。私のように人間ではないので、バイアスも少ないでしょう。LLM由来のバイアスはあるとしてもですね。
ということから、ロジカルシンキングをきちんともう一度学び直そうと思って本書を手に取りました。
結論、この本は一度読んだだけというよりは、使いながら指南書のように使うのがいいのかなというふうには思いました。
では次に、この本から自分が得た試験学習方法というよりは、新しく考え直さなきゃいけないなと思った試験についてこの後まとめていきたいと思います。
学び
佐々木は学びについてまとめていきたいと思います。今回特に意外だったのは、ロジカルシンキングってその意味で再現性を担保するものだと思っています。研究のように、どの人がやっても同じような結果や思考をもたらすことから、相手が納得できるし、説得できる要因だなというふうに思っています。もちろんその側面はこの本でもあったんですが、ここで面白いなと思ったのは、その手法を織り込んでオリジナルを展開させるという点です。
今だとAIも使って同じファクトにアクセスできる状態ですよね。それをもとに結論を出す場合って、誰がやっても同じような結論になりますよね。しかし、ロジカルシンキングを使うことで自分の色を出せる、自分がやるロジカルシンキングだからこそ意味があるものを出せる。ただし、聞く側からすると確かに筋が通っているなと思えるという、ある意味最強の方法をここでは述べているなというふうに感じました。
ということで、それについて自分の学びをまとめていきたいなと思っていますが、特にこれを読みながら感じたのは、結局新しい思考を生み出そうと思ったら、いろんな問題を考えてその回答への試行錯誤とか蓄積があるから、前提条件がストックされて新しい思考が生まれるようになっているところです。なので、この本で提案されている手法を使ったからといって、一足飛びに自分らしい手法や考え方が出てくるのではなく、これを使って積み重ねていった結果、積み重ねを元にして新しく大きく飛躍ができる。そういうものなんだなと感じました。
飛躍のための跳び箱を1個ずつ自分が思考しながら作っていくというのがいいところで、逆に言うと銀の弾丸はない。銀の弾丸はないからこそ、積み上げに価値があるんだなというのを強く思いました。
あと、延期的なストーリーをどのくらい書けるかというところも重要だなというふうには思いましたね。例えば、「So what?」という問いを立てて、それってどんな新しいことが言えるの?というところを考えることが大切です。そして、「何が新しいの?」という問いを掛け合わせることで、新しい視点やアイデアを生み出せるかどうかが重要だと感じました。
あとやっぱり思ったのは、自分の切り口をどのくらい持っておけるかというのが重要だなというふうに思いました。ロジカルシンキングをする場合でも、どういうふうに問いを立てるのか、問いをどういうふうに立てられるのか、どのくらい幅の広い切り口が立てられるのかによって、ロジカルシンキングの結果として得られるものも大きく変わります。
では、切り口をさらに増やすためにどうしたらいいのか、自分の視点を増やすためにどうしたらいいのかというところは、これから考えていきたいと思います。
追加で考えなければいけない今後の課題だなと思います。多様性っていう言葉を使うとちょっと安っぽい気がしてあんまり好きじゃないんですが、自分の中に別人格をいくつ持っているか、逆に言うと複数のバイアスをあえて持った人格をどのくらい作れるかっていうのが一つ鍵なのかなと思います。
例えば、自分だとAIとか健康とか運動とか、その力を見ることが多いんですけど、多分外から行くとTikTokみたいなショート動画であったりとか、インフルエンサーみたいな軸とか。
あんまり自分に興味がないもの、だからアイドルとか芸能とかスキャンダルとか恋愛とか、そういう視点のバイアスを持った別人格を作っておくって結構アリなのかなと思いましたね。自分が作るのもいいし、作らせるのも最初のうちはいいかもしれないけど、人格をトレースしてリリースするのも少し試してみてもいいのかなというふうには思いましたね。
あと、機能的な思考で法則を取り出して経験をレバレッジさせるというところが180ページあたりにあったんですけど、これって結構面白いなと思って。
いかに抽象化させるかって結構重要な能力だと思うんですよね。その中で例えば本書に出てくるのが、具体的なものが持っている具体性に縛られず、このように抽象化・昇華させる見方ができるようになると、ごく当たり前の日常が学びの宝庫になる。「真理は力なり」とあるんですけど、要はこういう新しい視点を持っておくと、アイデアを出すこと自体は別にそこに再現性がなくていいと思うんですよね。アイデアを出す方向だけ再現性があれば、その結果出てくるアイデアに再現性なんてなくていいし。
むしろ再現性がない方が人との差別化ができると思うと、再現性を求めるべきところと、それに再現性がなくていいところを結構明確にしておいた方がいいなと思います。やっぱり研究畑出身だと再現性って一にも二にも重要で、再現性がない研究なんて意味がない気もしないでもないんですけど。ただ、再現性があることが価値になる部分と、再現性がないから価値になる部分って結構あると思っていて、特にビジネスだと別に再現性がなくても当たればいいというところは正直ある気がしています。
そのために再現性のない仮説を立ててPDCAを小さく回し、結果が出れば大きくしようというのができるのがビジネスだと思います。再現性の重要性があるべき部分と、むしろ再現性がない方がいい部分というのは、結構自分の中で明確に分けた方がいいかなというふうに思いましたね。
ただ、機能的思考がいい部分というのは、情報の集め方を考えられるというところだと思いました。
どんな示唆をこれから得られているかとか、情報の海に溺れちゃうことがあると思うんですけど、私の考えた比喩だと、情報という砂漠に自分がどういう磁石を持っていくかによってくっついてくる砂鉄は違うだろうというところですよね。情報の海の場合、これだけ情報が溢れていると、自分が注目できるものってだいぶ限られる気がしています。
なので、自分がその情報の砂漠に突っ込む磁石が何を引き付けるような磁石なのかっていうのは、だいぶ意識してから情報の海に飛び込まないと、なんとなくで情報を過多の世の中に突っ込むのは結構危険だよなとは思いましたね。情報を見るときの情報の海に溺れない方法、情報の砂漠からきちんとした情報を取り出す方法を考える必要があるなと思いました。
あと、帰納法だとやっぱり多段階的にうまく考えることの重要性って結構大きいなと思いました。
特に自分のように、まだタスクをドーンと振られた時にどう分解していいか分からない場合って、一旦フレームワークに則って帰納的に分解していく方が確実だなと思いますよね。自分が解決できるレベルまで下げていくことで、タスクを小さくしていくうちに自分が扱える範囲になり、一歩目を踏み出せる。やっぱり今だとタスクをもらった時に、じゃあ次どうしたらいいかなっていう打ち手が結構5、6個出てくるけど、まだ大きいということがあるので、出てきた5、6個のうちでさらに分解していく必要があると思います。
さらに小さくしていくことで、5個や6個の打ち手をさらに分解して、合計20個とか36個くらいの打ち手にしていくという問題の切り分け方の能力も、やっぱりこなして慣れていくしかないんだろうなとは思いましたね。自分の手に負えるレベル感にまでいかに下げていくか、そのためにどういう知識、というか視点が必要なのかを考える必要があります。
例えば、分析者視点なのか、広告主視点なのか、マネージャー視点なのか、事業視点なのかといったいくつかの視点から物事を分解できると、より具体的な打ち手が見えてくるのではないかと思います。
上司ともブレがない、かぶらない分解の仕方ができるのかなとは思いました。
まなび
この中で多段階的な基本的思考のところだと、問題は3Cに分けるっていうところがあります。3Cっていうのはカスタマー・顧客、コンペティター・競合、カンパニー・自社みたいな切り口があるんですけど、これを自分の業務に置き換えて分けていくっていうのは、ちょっと自分の中に使えるような思考かなって思いました。自分の場合は。
DS視点でどうか、広告視点でどうか、営業視点でどうか、論文視点でどうか、というのをさらに追加できるんだろうなと思いました。それぞれの視点から見ていくと、多分ビジネス的な観点でも見られるようになるし、マネージャー的な観点でも見られるようになるし、仮に今後自分が独立した場合にもこの思考法って使えるので、これは持っていた方がいいよなというふうに思いましたね。結構本当にここから持って。
得られた視点って多くて、多分自分のメモとかハイライトの数を今Kindleで確認しながらこのブログを書いているんですが、過去最多じゃないかなというふうに思いますね。
ビジネスで使える視点を下にまとめると、どこから仮説が出てきたかよりも、その仮説がどう役立ちそうかっていうところにもっと目を向けた方がいい、というのは確かにそうで。例えば、上司との会話の中で出てきたアイデアだからといって、必ずしも素晴らしいものかというと、それを妄信的に信じることはできないなというふうに思っています。もしかするとネット上で見たものがビジネス的には有効性を持つかもしれない。なぜなら、上司が考えるものというのは、もしかすると既にもう実行されている可能性もあるし、実行した検証したけども上司が忙しくて忘れている可能性もあるし、また逆もありますよね。知らないから試していないだけで、本当はめちゃくちゃ効くっていう提案を上司がしてくれている可能性もあるんで、一概に言われてはいないんですけど、ネット上でも見るような「誰が言ったかが重要じゃなくて、それが役に立つかどうかが重要だ」というところ、特にビジネスではそうだなというふうに思いました。
結構自分は論文とかの観点では誰が言ったかって結構重要だなと思っていて、スティーブン・ピンカーが言ったのかとか、誰が言ったかによってその発言の重みが変わるなと思うんですけど、その視点はありつつも、その仮説や言説が役に立ちそうかっていう視点で見直さないと、これって私の持っているバイアスだよなと思いましたね。そんなところが今回の学びなんですが、テキストとしてすぐにメモにして、自分が考えた時に目につくようにして、この考え方ができているかな、圧入とかそういう考え方ができているかなっていうのを確認するための学びに他ならないと思います。
明日フレームワークとして繰り返しながら覚えていかないといけない内容も結構あるなとは思いました。なので、この章については何回も読みながらまとめていくしかないですね。もうちょっとこのブログを終わらせた後に一番にやるのは、80ページにあった「5つの力」と「思考力の成熟度モデル」というところに、自分の成熟度を踏まえて次の打ち手を考えていこうかなと思います。なので、コンショーについては何回もやりながら求めていくしかないですね。このグラフはリード一番にやるのは80ページにあった5つの力と思考力の成熟度モデルというところここに自分の成熟度を踏まえて次の打ち手を考えていこうかなと思います。
まとめ
AIが発展してきてデータ収集だけが簡単にできるようになった今だからこそ、誰が考えてその成果を出せたのか、仮説が出したのかって結構重要じゃないかなと思っています。データ収集が簡単になったから、私が分析したこと、私が得た知見がどのくらい役に立つかっていう、自分がリサーチをして仮説を出すことの価値をどうやって出していくか。その一つにこのロジカルシンキング、プラス自分の情報の張り方ってあるよなと思います。先日見た動画でも西田先生が誰かの動画内であったのが、今までだったら東大生がもうちょっとお前たち考えてきたでしょっていうような授業の資料がAIが考えて少しだけ体裁を整えたんだろうなっていうような資料がだいぶたくさん出るようになったっていう話がありました。この話がどのくらい正しいかどうか、本当にそうなっているのかどうかっていう裏付けはちょっと私ではできません。できないんですけど、そういう傾向はあるよなとは思います。そういうふうに楽な方に人が流れていく可能性はあるなと思っています。
今こそ自分の頭をどこに使うのか、ある意味情報収集に使わなくていいというふうに仮定するなら、そこから仮説検証、特に仮説を生み出すところにマンパワーを使えるはずです。ただ、仮説が良ければ情報収集の質も上げられるはずと考えると、やっぱり仮説をどのくらいうまく立てられるか。この能力を上げていくことが、今後AI時代に求められる能力なんじゃないかなと思います。今後どうなるかはちょっと分かりませんけど。
というのが本書『新ロジカルシンキング』から得た私の学びです。ここまでまた音声入力をしながらこのブログを書いているんですけど、どのくらい誤字脱字があるのか一切確認せずにブログをアップするあたりに、もう私もだいぶ怠惰だなとは思いつつ。手書きで書かないからこその問題点とかはあるよなというふうには思いますよね。うまくまとまっているかどうかは分かりません。ただ、話し言葉でうまくまとめないと結局会議とか人とのコミュニケーションってだいぶ音声に頼るところがあるんで。
徐々にこのブログも音声入力だけの質の良い構成で書けるように、今後このロジカルシンキングの学びをもって改善していきたいと思います。今後の成長に期待しています。



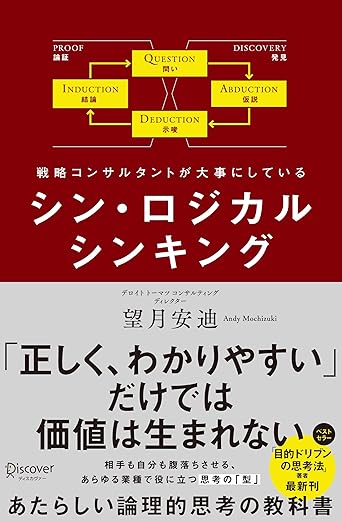

コメント